幸福論(1)
1996.7.10
京都大学 大学院エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学教室
1.緒言:人間と社会との目指すもの
我々は何かの目的を持って生きているのだろうか? 我々個人からなる社会も、何かを目指して進んでいるのか? これらの問いには、幸せを達成するためという答えが自然なようである。それではすぐに、では幸せとは何ですかという次の質問が生ずる。また果して幸せは“達成”など出来るものかということも判らない。この難問、通常は考えないで済ますのが世のしきたり、というもののようである。 それに代ってもっと明確なわかり易い目的、例えば、景気を良くするとか、病気を治すとか、新しい超伝導材料を見付けるとか、太陽エネルギーの新しい利用法を見付けるとかに、皆が我を忘れて熱中することになっている。という訳で、我々の日常のあくせくとした忙しい活動は際限なく活発にならざるを得ない。例えていうならば、暗がりで物を落とした場合に、落とした場所が暗くて探し難いので、本当はそれを落とした場所ではないけれども、もう少し明るくて探し易い場所を一生懸命探しているようなものであろう。本当はそこに目的物は無いから、いくら探しても見付からない、お陰で探すという仕事は幾らでも続けることが出来る訳である。そこで、ヘソ曲りにも、恐る恐る、本当にそれがありそうな暗がりを探って見ようというのがこの講義の目的である。
もちろん、暗いところを探そうとした人は大勢いたし、今もいる訳だけれども、ここでは今までのやり方と少しでも違ったやり方をしたいと企てている。そのやり方というのは、先ず、幸せになろうとする人間と社会と、そしてそれらの存在する自然界とについて出来る限り簡潔に総括してみる。つまり、幸せになるという対象である我々自身と、その置かれた環境を徹底的に洗い出して見ることから始める。インドのジヤイナ教の有名な例え話しにある、象の形を調べるやり方のように、シッポだけ触って象とはヒモのような物だとか、腹だけ触って、いや壁みたいだとかいうことにならないように心がける計画である。つまり工学的に、まず境界条件を決めてから解を求めようという訳である。
2.所願無量・経済の原理
先ず始めに考える必要のある事は、我々が社会活動をしていること、すなわち集団で暮らしている理由についてである。もちろんこれは、個人がてんでにバラバラに暮らすことの不便さを想像すれば明白なように、便利さ、暮らし易さのためである。いいかえれば、これはそれが経済的に有利であるからといえるが、経済的とは、人間の種々の欲望を満たす手段がより容易に達成出来るということである。人の欲望の尺度、見積もり手段として用いられるものはお金であり、このお金を目安として、我々が社会生活をすることが我々自身をどんな環境に置いているのかを考えて見ることにする。
人間の欲望には際限がない(所願無量)。これに対して地球上の資源、環境は有限のものであり、有限なものをもって無限なニーズを充たそうとすれば破滅に至ることは自明である。これは徒然草に書かれている(217段)話しだが、今の社会の経済活動の急所を衝いている。経済成長率の維持向上が最大課題であると世界中の国々が公言し、それが当然であるとされている事ほど不思議な話しはない。成長率というのは複利法で借金をするように雪ダルマ的に経済規模が増大する事を意味している。環境問題における二酸化炭素のように、経済規模も増大は困るもの(地球の容量に限度があるため)であるはずで、世界的規模で「総量規制」がなされるべきであろう。
しかし、所願無量は人間の本性であって、これを充たそうとする心が人間の幸せ、幸福感につながっている事が問題を複雑、困難にしている。他人(他国)は、どうなろうと知らん、俺のやりたいようにさせてくれ! というのが大多数の人の気持ちであり、これが、個々の人間の能力を最大限に発揮させる原動力となり、その結果として、アダム・スミスのいう自由放任による国の富の増加につながる訳である。
所願無量は、具体的には、ウエーバー・フェヒナーの法則として知られる人間の感覚についての実験結果によって定量化して示されている。すなわち、ある刺激の分別閾値jnd(just noticeable difference) は、刺激の大きさに比例することが示されている。
jnd=ΔI/I
ある時に刺激が大きくなっても、人間はすぐにその大きくなった刺激に慣れるから次の刺激へと増加を求める。しかしその時には増えた刺激を基とするjndが必要となる。すなわち、複利的に刺激の増大を望んで行くことになる。
所願無量のもうひとつの困った点は、これが野放しになると、貧富の差が増大して社会的不安定構造が生ずることである。公平なルールで社会が運営されても、経済活動は一種の賭けのようなもので運、不運があり、資本の集中は時間とともに増大する性質がある。したがって、貧富の格差は自然に増大する。
この点の解消については、ケインズが、種々の規制、とくに利率のコントロールによって効果をあげ得ることを示した。しかしケインズの理論も、所願無量の規制をしている訳ではなく、成長を前提とした上での規制による富の再配分法にすぎない。
所願無量の本能を充たしつつ、成長を規制する方法を求めることが、人間の幸福感を損なわずに社会を安定させる唯一の道である。コントロールパラメーターには税制を利用することが考えられよう。それには、所願無量による富の獲得後の満足感の緩和時間の適切な利用、すなわち儲けの喜びを味わう時間を与えてその後で巻き上げる方法を考えることである。いうならば朝三暮四をうまくやることだ。
3.心の問題・哲学の目的
我々の生きる社会を現実的に動かすのはお金・経済だけれども、これを前節のように所願無量だけで割り切ることは実は本来間違っている。 人間だれしも、所願無量の本能を持っており、したがって社会全体を動かす経済的原理はその規模の指数関数的(ネズミ算的)増大であるけれども、人間の幸福を考えるとなると、いわゆる心の問題が前面に出て来ることになる。心の問題を、ここでは哲学の歴史を概観し単純化して、それが何を考えることになるのかまとめてみたい。
心の問題を表立って人間が考え、記述を始めたのは中国、インド、ギリシャほぼ同時、紀元前6世紀頃のようである。道とか、法(ダルマ)とかイデアとかいう目に見えない、体験できない、観念の上にだけあるもの、すなわち形而上の概念はそれ以来人間、社会の悩みの種であり続けてきている。
端的にいえば、我々は何者で、どこから来てどこへ行こうとしているのか、という問いである。これに付随して生ずる問いは、世界の始まりはあったのか、無かったのか、宇宙は有限か無限か、世界の運命(未来の事柄)は決まっているのか、偶然によって決まる不定なものか、などであり、これらの問いは多くの場合、絶対者(神)の存在、不在の論議へとつながって行く。
これらの問いは、もちろん、いくら考えても答えの出ようはずが無いことは常識で考えれば当然だ。そのことは、例えば原始仏教の14難無記といわれる問答で、これらの14の形而上的質問にお釈迦様は、答える代わりに、そんなつまらん事を考えずに目先の現実的修業をしなさいと悟している。その通りで、そんな事は考えなくても現世の幸福は十分に達成できる訳なのだけれども、それでも、ふと我に返って見ると、この形而上の問題は喉に刺さった魚の骨のようにチクチクと痛んで何となく安心な幸福感に浸る事を妨げるもので、気になりだすと、人間そのことだけが気になるものでもあった訳である。
したがって、数え切れない多くの人々(哲学者)がこの問題を論じており、その各々が、俺はこれを解決した! と叫んで書物を書いてきた訳である。もちろん、それらの結論には通常数年を経ずして別の結論が現れる訳で、今日に至るまで、そのあり様は続いている。 そのような論議にひとつひとつ付き合っていると哲学者の後を追いかけなければならないし、それをやっていると何だか哲学者が本当に偉いような気になる、いわゆる“哲学病"に取り付かれかねないので、ここではこれらの論議の流れをバッサリと2つに締めくくって、人間の思考法の実験結果として受け取ることにしたい。
形而上の問題は、考えることだけでは解決不可能なのだから、この問いから逃れるためには、 何とかこれを考えないで済むか、 あるいは解決したと考えることが出来るかの2つしか道はない。 の典型的な例は、中世のキリスト教徒(スコラ哲学)の受け留め方、すなわち、形而上の問題は credo quita absurdum (非論理的であるが故に信ずる)として神への無条件信仰に走ることであり、 の典型は、デカルトが考えたように、cogito ergo sum (我考える故に我あり)、すなわち考えに考えた末、神の存在を証明したと受け取るやり方である。 もちろん、これらははっきりと神といわなくても老荘思想のように無為自然といってもよいし、日本で盛んな仏教のように念仏を唱えるだけで(専修念仏)そちらの方のことは総て解決というやり方もある。
一方、昔は形而上の問題と考えられてきた事柄が、かなりの部分、実は形而下の事柄である事も判ってきている。つまり考えるだけではなく実証によって明らかになってきた部分もある。 例えば、天体の運行にしてみても、天動説で説明しようとしていた時代には星の動きが複雑過ぎて説明し切れず、神の攝理と見られていたところが、地動説に切り換えることによって単純明快な規則で説明出来てしまった。別の例としては、人間は初めから人間として存在したという前提(これはいずれの世界の神話でもいきなり人間が登場することになっていることによる)で、世界の初めと終わりを考えていた間は、生命の問題は純粋に形而上のことだったけれども、進化論の証明によって、少なくとも形而上的な面は原始生命の発生機構のところまで後退(35億年程)してしまった。
このような形而上学の領域の変化を見ると、従来の哲学者のように、判った判ったと直ぐに解決を急ぐことは良くないらしい事が判ってくる。つまり、今判らないことは判らないことにして問題を棚上げしておけば、それは、前述の でも でもない(あるいは でも でもある)けれども目先の世の中の幸福を考える支障にはならずに済みそうである。そうすることによって、14難無記の現代版というか、あるいはお釈迦様はやっぱり偉かったといっても良いけれど、喉に刺さった骨の痛みは少なくて済みそうである。
もちろん、こんな理屈はすっぱりと抜きにして信仰に身をゆだねる人はそれで全く結構であろうし、幾ら年代が進んで世の中変わっても、そのような人々の数は今と変わらないであろうことは容易に想像できる。人間の頭脳のハード、ソフトは千年や二千年では変化しないものだと思われる。
4.自然のしくみ
人間の幸福を考えるためには、我々人間の存在している自然界、つまり我々をとりまく環境についての知識と、我々の周囲での事象の変化についての知識、さらには我々の身体そのものの成り立ちについて、その根本的なところを把握しておく必要があろう。すなわち、幸福になるのは我々自身の身体であって、それが幸福になるステージは我々を取り巻く自然界である。そこでどんなルールでドラマが進行することになっているのかを知っておこうというのがこの章の目的である。もちろん、自然の仕組みの総てを学ぶことは無理なので、身近かな3つのトピックス、 我々の活動の源であるエネルギー、 自然の変化を支配するルールとして最近注目され始めたカオス、 人間は人間から始まったものではないとすれば、我々は生物としては何なのか。について要点を見ることを企てる。
4.1.エネルギー
エネルギーは、仕事であり、光であり、熱であり、音であり、食糧であり更にまた物自身でもある。つまり我々の活動は総てエネルギーの移動や表れ方の変化そのものといえる。このエネルギーについての身近かな科学的取り扱いを述べるのが、熱力学という学問である。ここではこれに従って、エネルギーの本質的性質を述べる。詳しい説明の代わりに例によって考える。図-(a)のように80℃と20℃のそれぞれ1リットルの湯と水とがある。
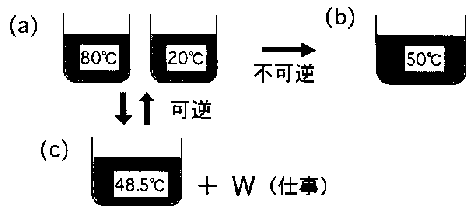
この湯と水とを混ぜれば図-(b)のように2リットルの50℃の湯が出来ることは誰でも判る。元の(a)であったときと(b)になった時とではエネルギーの量は変わっていない。しかし(a)と(b)の状態には明らかに差がある。その差、つまり何が変化したかの目安がエントロピーという量で計られる。(a)の状態から(b)の状態へ変化することによってエネルギーは不変、エントロピーは増えるということになる。どれだけ増えたのかは、エントロピーを増やさずに仕事を取り出しつつ80℃の湯から20℃の水へと熱を移す場合との違いを計算することによって見積もれる。その結果は(c)の状態、すなわち48.5℃の湯と、とり出した仕事Wとに分かれた状態となる。 この仕事Wを使えば48.5℃の2リットルの湯は元の80℃と20℃、1リットルずつに戻れるから、エネルギー学(熱力学)的には(a)と(c)の状態は等価である。このことから(a)から(b)に変化する時のエントロピー増加は、
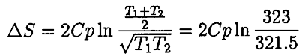
ということが計算できる。
さて、80℃の湯と20℃の水は混ぜると50℃になるけれども、50℃の湯は、自然に80℃と20℃とに分かれてはくれない。エントロピーが増えるということは、自然に起こる変化は一方通行で一回起こったことが元に戻ることが無い、という厳然たるルールを端的に示すものである。 元に戻れるのは見かけは異なるようでも、何も実質的変化の無い場合、(a)から(c)への移行のような時のみである。
変化が一方通行だけという原理が宇宙全体に適用されると、宇宙は究極状態ではいわゆる“熱的死”すなわち全宇宙の温度が等しくなって、もうそれ以上何の変化も起こらないところにまで一方向に突き進むという予想に至る。その予想が正しいのか否かは解明されていないが、今の目的つまり千年単位で地球上の我々の幸福を考える範囲では、エントロピーの増大すなわち、自然現象の一方通行は疑う余地なく成立している。我々は太陽の中で水素が核融合してヘリウムになる時に発生する高温の光エネルギーが地球に到達して、雨や風や植物生長などに使われてエントロピーが増大して、より温度の低いエネルギーに変化する過程を利用して生きている訳である。石油や石炭も過去の太陽エネルギーの極くわずかの地球上への蓄積である。
いずれにせよ、エネルギーの本質を学んで参考とすべき点は、エネルギーの再利用などという虫の良い話は厳密な意味では不可能ということである。覆水盆に返らずで、一度利用したエネルギーは一方通行で、元の温度の高い(質が高いといわれることもある)エネルギーには戻れない。ただ、利用法を改善してケチケチと、最大限の利用をその一方通行に際して実行する工夫をすることが出来るだけである。更に大切なことは、千年単位で考えて、我々が安心して利用できるエネルギーは太陽エネルギー以外には絶対にないということである。
4.2.カオス
カオス理論は1960年代から始まったもので自然科学の重要な分野としてはとても新しい。新しい分野は多くの驚きを我々にもたらしているけれども、まだ完成されていないし、マユツバ的な要素もありそうである。端的にいうならば、これ程驚天動地の新説なのに、カオスでノーベル賞をもらった人は未だいない。しかし、その示唆するところの事は、人類の歴史始まって以来の疑問に答えるかも知れないし、固定観念を根本から覆すかも知れない。
その疑問とは、ずばり、哲学の章でとり挙げた、偶然はあるのか無いのか、未来は決定しているのか否かである。仮に、神といえども明日の天気が予測出来ない、ということが証明されたとすると、一寸先は闇である我々と神との差が縮まって、形而上学の一部が形而下に移ってしまう。カオスはそのような本質的予測不可能性を示唆している学問である。そんなに大それた学問だけれども、その基本は、あまりにも簡単な原理で説明出来てしまう。その原理とは、第2章の経済のところで出て来た複利法の原理である。カオスという言葉は混沌、すなわち、ある情報が完全に失われることだと定義出来よう。すると、始めに持っている情報の精度、例えばある物体の位置を示す座標の桁数が10桁であったとして、1回に10%ずつ情報の失われる操作を250回繰り返すとその10桁(100億分の1の精度)全ての情報が無くなる。つまり、繰り返すという操作の数が、1,2,3,・・・・・・・・n,. と直線的に増える時に、情報の失われ方は(1+α)n という指数関数的に増えるという事である。 日本刀は繰り返し鍛造によって鍛えられるが、1回に1/2の厚さに延ばしてこれを折りたたんで又延ばすという操作を10回繰り返すと、元の鋼の厚さは千分の1、20回繰り返すと何と百万分の1の薄さの組織となって刃の中にたたみ込まれる。この“フラクタル”と呼ばれる自己相似超微細構造(ミクロな部分の構造がマクロな構造と相似であること)が日本刀の優れた性質を生む訳だけれども、元の百万分の1にまで微細化するのに、たった20回の鍛練ですむという所にも基本的にカオスの発生原理である繰り返しの恐ろしさをかいま見ることが出来そうである。
今、現在持っている情報から我々が未来を予測出来るということは自然現象の移り変わりが、現在の状態(我々が情報を持つ持たないに関係無く)から、あるルールにより次の状態へ移ることの繰り返しであるためである。実は、このルールが如何に厳密なルールであり不変であっても、1回の繰り返しで必ずある量の情報が失われるので、繰り返しを続けるうちに、いずれは今の状態からの推量が不可能な状態へと移ってしまうという事態が発生する。
仮に今の状態を無限の精度で決めることが出来たとしても(神は無限の知識を持ち得る)繰り返しにより失われる情報の量が更に強い無限であれば、結局情報は全く失われてカオスとなる。繰り返しにより失われる情報の量の増加する強さが、元の無限の情報量を超えるという自然の原理が仮に神によって作られたと考えると(全ての原理は神の決め給うたもののはずである)神は自ら未来を予測することの不可能性を創り出したことになる。神とはこのような人間の知恵による考察の範囲を超えた全能の存在であるから、ここで神という言葉を持ち出すことは意味が無い、という話がボエチウスの本に書かれている。そうであるかも知れないし、そうでないかも知れないが、少なくとも従来、形而上学の範囲として悩んできた問題の一部を、形而下に移す必然性が生ずることになりそうであり、そうなると形而上の問題は今までとは異なった所に移さなくてはならない。
4.3.生物としての人間
ダーウィンの種の起源を読むと、よくもあの当時の少ない知識であれ程大胆な仮説を、あれ程はっきりと明言したものだと驚かされる。ダーウィンの仮説は要約すると、
人間を含む全ての動物、植物、の始まり、すなわち生命の起源は、元はたった1個の 生命に帰着する。この1個の生命から進化によって、世界に存在するかくも多様ですばらしい生物が出現した。 種の進化は親が獲得した形質が子に伝わるのではなく、偶然に環境に都合の良い形質が現れた時に、適者生存(自然淘汰)の原理によってそれが種の中に広まることによる。
これらの、とくに の、全生物の始まりが1個の生命に帰着するという仮説は全く驚くべき事であるけれども、現在の分子生物学の先端的研究結果によっても、これが証明されているという事である。
さて、人間は人間からスタートしたのでは無いという事を我々は受け入れて、その上で心と身体等について論議する訳だが、ダーウイン以前の人々は、その前提ではなくて、何万年か前に急に人間が出現したという前提で、形而上の事柄を考えざるを得なかった訳である。これを、我々は笑っている事が出来ないことに気付かねばならない。我々の今もっている自然のしくみの知識は、今から千年後の世界での知識と比べれば、恐ろしく未熟なものであるに違いない。どこまでが形而上の問題で、どこからは形而下の問題かは、したがって今の状況とはかなり変わるということを考慮に入れて我々は議論をすべきであろう。進化論の証明はこれの良い例のように思える。
ここで生物としての人間について現在出されている仮説、証明されたとされる事柄を総括してみる。
機能(function):「驚くべき仮説」、DNAの発見者の1人クリックによると、人間の魂、心、精神は脳(ニュ-ロン)の働きとして説明が可能となるであろう。
構造(structure):人体は約100兆個の細胞から成っているが、これらは全部が1個の細胞から分裂によって発生したもので、全部基本構造は同じである。しかし機能は著しく異なる。全ての細胞の1個1個がその個人の個人たる全情報(ゲノム)を有している。
人類の祖先(origin):全ての人類の祖先は約10万年前にはアフリカに住む1人あるいは数人の人々に帰着する。(ミトコンドリア・イブ)
進化の機構(evolution mechanism):生物の進化のメカニズムは突然変異の固定による。親の獲得形質は遺伝しない。全ての生命は約35億年前に1個人間ないし数個の原始生命から始まった。
5.幸福論・人々はどう考えて来たか
幸福とは何を意味するのかという定義は難しい。古代の哲学者達は人間の幸せは社会の善に合致する徳の高い生活をしてこそ達することの出来るものであるという基本的考え方を中国、インド、ギリシャを通じて持っていたようである。そこで端的に、ボエチウスが書いたように人は皆幸福を求めて生きているものである、といえばなるほどそうなのかと誰しも納得出来そうである。ではその幸福とは具体的にどんな状態かそしてそれを達成する方法は何かという事が問題となる訳で、数多くの人々が、幸福あるいは幸福論について本を書いている。
さて、これらの本を通読すると、実に様々な幸福論があるものだと感心させられるが、その基本に流れるものを抽出して、 幸福でいるための物の考え方や行動のとり方、つまり生活の知恵の記述、 第3章で触れた形而上(心)の問題を如何に解決するか、に分けて読むと読み易い。 の方は第3章で考えたので、ここでは繰り返さず、 について見ると、人間の考えることは、かなり同じ路線にはまるものだという気がする。しかし、いずれの生活の知恵もひとつひとつ納得のいく事柄で、大いに参考にはなると思う。これらの中で、特に幸福というものの特質を端的に衝いている言葉は、「幸福になった後の、幸福論は」とか、「幸福になったらその後どうするか」という表現である。これらの表現は、デニス・ガボールの本「成熟社会」で取り挙げられている成熟した社会の目指すものという問題と共通している。すなわち、幸福は達成されて、はいおしまい、というものでは無いところが問題として難しい訳である。この問いは結論の所で考えることにして、ここでは、以下に、幸福論について書かれた本の幾つかを挙げて、その触りを書き添える。表
6.結論・千年後の世界
桜がり、雨は降り来ぬおなじくは、濡るとも花の蔭に宿らむ
平安時代の貴族、左近衛中将、藤原実方はある年の春、東山に花見に出掛けて、にわか雨に会い、花の下に立って詠んだこの歌が評判となり得意になっていた。天皇(一条)にまでその噂が伝わったが、藤原行成(能書家、三跡のひとり)に、「歌は良いが、わざと雨に濡れるなど感心しない」と告げ口された。これを恨んだ実方は殿上で行成と喧嘩して、行成の冠をたたき落とし、庭に投げ捨てた。行成が慌てずに人を呼んで冠をとらせ、平然と去って行ったのを運悪く天皇に見られていて、行成は蔵人に抜擢、実方は「歌枕を勉強してこい」といって陸奥の地へ左遷された。赴任先の宮城県で、人の諌めを聞かず道祖神の前を馬に乗ったまま通ろうとして、実方は落馬して死んでしまった。実方の死んだのが998年ということだから、このストーリーは今からちょうど千年前頃に起こったドラマという訳である。
話の真否はとにかく、千年昔の人間ドラマを我々は今もって生々しく実感できることは確かである。 例えば、我々研究者と呼ばれる大学等にいる者は、人の評判になるような“良い”論文を書くことにこだわっているが、“良い”論文と思っていたのにケチを付けられた、ということは有りそうな話だ。そのために普段はおとなしい先生がカーツとなるということも容易に想像できる。似たような状況は世間のどんな分野にもあるであろう。 我々は今、自動車、飛行機、冷暖房、コンピューターを使い、衣服も食事も千年昔には全く想像も出来なかった生活をしている。その上、千年前にはおよそ想像も出来なかったであろう恐るべき多くの知識、ビッグバン、ゲノム、カオス、エントロピー、などになじんでいる。ところがこんなに大きな身の回りの変化も、人間の感情の動きの基本的なところには、何も変化をもたらしていないことが歴史を読むと判ってくる。我々は皆、千年という年月はすごく長い期間であると思っている。したがって今から千年後の世界を想像せよといわれても誰しも直ぐには頭がめぐらないであろう。しかし上に述べたように、千年昔と今を較べて見ると、それはほんの昨日のようにも感ずることができる。つまり、千年後の世界は、今の我々の世界とそんなに掛け離れたものでは無いのである。
ところで、千年昔といえば、25年を1世代として約40世代である。自分の親は2人、祖父母は4人、曽祖父母は8人、・・・・・・というように40世代さかのぼると我々は誰も例外なく、240≒1兆人の祖先がいることになる。平安時代の日本の人口はおそらく多く見ても1千万人位だろうから、その頃の人々は皆んな、つまり、実方も行成も、それから恐れ多くも一条天皇も含めて何重にも我々の親戚であることには疑いの余地が無い。
その頃に、喜んだり悲しんだり、幸せであったり、不幸であった人々がみな我々ひとりひとりの共通の祖先であるとは愉快なことではなかろうか。我々は身の回りの人々の幸せを自分の幸せと感じ、悲しみもまた自分の悲しみと感ずることは皆同じである。千年昔の実方の憤慨も、行成のしたり顔も我々は自分の親戚として分ち合う気になることが出来る。こう考えると今の自分の幸せや不幸せも時の流れの中のひとコマに過ぎないことが実感されよう。数え切れない過去の幸せや不幸せの結果として今の我々の幸せや不幸せがあり、今の我々の幸せや不幸せが自分と少しでも係った総ての同世代の人々を通して未来の数え切れない幸せや不幸せの原因となるという訳である。
衣、食、住の最低レベルは充足されないと何といおうと不幸であることは、間違いなく動物としての人間の本性である。 戦後の食糧難を知る者にとって、空腹で幸せなことは絶対にないと断言できる。断食をして修行する人ももちろんいるが、いつでも食べられるという事が判っていれば断食を楽しむことは容易である。本当に食べ物が乏しい時に断食する人はいない。この最低レベルが満たされた後の幸せが何かを考えることは、ほとんど人間とは何かというのと等しい難問である。人は様々な異なる感覚をもって幸福を感じ、不幸を感ずる。ある人の幸福は別の人の不幸かも知れないとは良くいわれることである。人は生まれ持った性格(脳の機能の違いであろうか)によって小さなことで幸せになれる人もあり、いつも不幸な人もいる。また何かと運の良い人もいるし、いつも不運な人もいる。一生かかって段々と幸せになる人もいるし、それほどでもないのに一生を振り返ると結構幸せだった人もいる。 また一生、いつもみじめであったのに、一瞬の輝きで最高の幸せを得る人もいるであろう。
いずれにしても人間の体に100兆個もの同じ基本的構造の細胞がそれぞれ異なる機能で働いているのと同様に、1個人は同世代だけでなく過去と未来の数え切れない人間のうちの1人にしか過ぎない。それらの人間は皆同一の基本構造を持ちながら、ひとりひとりが皆異なる性質を持って異なる機能で動いている。自分の幸せ不幸せは今生きている我々が作ったものであると同時に我々の先祖が作ったものでもある。 千年昔の文化を我々が今味わうことが出来ると同じく、千年後の世界に生きる人々に今の我々の文化をエンジョイしてもらえることを望まぬ人はいないと思う。つまり、人間の幸福は時間を含めた考えによって決まってゆくもので、定常的、不変の幸福というものは無い。 つまり、幸福は達成されてめでたし、めでたし、というものではない。ささやかな幸運も、それを守ろうとした途端に“不幸せパターン”に陥っていることになる。いつでも身を捨てる気持ちでいないと“幸せパターン”に乗れないのが人間の宿命であろう。過去、現在、未来全部考えに入れて、今を生きることは、どんなことかを考えて見ることのできるのが人間の特性であり、我々はこれを意識して生きることにより誰しもがどんな状況でも幸福でいられる。
次の和歌を一偈(ゲ)(しめくくり)と受け取って、この歌を生きて実感できるように今の生活を頑張ること、頑張ることの出来ることをもって幸福と考えたい。
ながらえば、またこのごろやしのばれむ、憂しと見し世ぞ今は恋しき。 (新古今集、藤原清輔)
Written by Shingu : 2001年04月14日 10:24