一言でわかる倫理学:
緒言
「倫理学とは人の行いについて、それが正義にかなっているか否かを判別しようとする学問である」これは「倫理学の方法(Method of Ethics: Sidgiwick、1874)」の冒頭に掲げられている倫理学の定義である。
ケンブリッジ大学教授であったシジウィックの提言はなるほど分かりやすい、と一読して感じるけれども、さてよく考えると、何も言っていないようでもある。つまり、倫理とは何か?という問いを、正義とは何か?という問いに置き換えただけ、と言えなくもないからである。
我々は何かの行動を毎日しているのだから、意識的であれ無意識であれ我々の取る行動が何故それであって別の行動ではないのか、常に判断を下しながら生きていることになる。その判断の基準はどこにあるのか、‘正しい’判断を心がけるに当たっての基準をどこに求めているのだろうか?はたして、いま我々が判断の拠りどころとしているものより‘優れた’基準があるのだろうか?
判断の基準はどこにあるのか?という視点で古今東西の歴史、文学、聖典、哲学書などを調べると、およそつぎの三つの基準が考えられる。
(1)絶対者(神)の示したもうた基準に従う。(カント流に言えば、定言的命法がある)。
(2)目的に合致した行動を良しとする。(アリストテレス流に言えば、人類の幸福を最高目的とする)。
(3)常識的な判断。(孔子流に言えば、黄金律:己所不欲 勿施於人)。
倫理とかモラルとか道徳などの言葉で呼ばれる人の行いのあるべき姿は、いずれも以上のどれかを拠りどころにした規範だと見ると、自分の行動の根拠が理解し易いであろう。本稿は、以上の三つの分類について調べた上で、現代社会に合致した倫理観がどのようなものであれば良いかを考えることを目的としている。
1. 定言的命法(Categorical Imperative)とは何か。
この言葉はカントによって取り上げられたもので、一般にはなじみがない。しかし、説明(道徳形而上学原論:Grundlegung zur Metaphisik der Sitten, 1785)を読むと容易におよそ何を言おうとしているのかが判る。カントの著書はいずれも難しそうで近寄り難いが、結びの所に極めて端的に、倫理(道徳:Sitten)についてサマライズしている。
カントは人が何をなすべきか、を考える時に目的に応じて行動を考えるのはよろしくない、人の取るべき行動にはアプリオリ(先験的、つまり行動するまえから決まっている)な必然性がある、と見ている。
それは、絶対的必然性だから、何故そのようなものがあるのかは当然説明できない、としている。何故、という問いをできない事は、しかし、決して理性を非難することではない、とも言っているが、その理由は、何かを理性で説明しても、結局さらに突っ込んで説明することが必然的となる。そうなると、説明の説明をするハメになって結局理性の満足は先へ先へと無限に引き延ばされる。だから、始めから、こうあるべきだという定言的命法を受け入れなければならない。という論法である。
カントは神という言葉は使わないが、世界にはなんらかの最高原因がなければならない、と言っているのだから、それは神と言い替えられるものであろう。絶対、とか、無限、とかが関与する事柄は‘神’の領域であると見ることは、それから生ずるパラドックス(矛盾)をしのぐ、最も有効な方法なのである。
疑うことなく我々が信じることの出来る、行動規範、道、を持つ事ができれば社会的な問題の多くは上手く処理できていくであろう。少し考えると数十年以前の日本の社会は、神仏を敬い恐れる気風が現在に較べて遥かに強く生きていた。そんな事をしたら罰が当たる、という言葉が日常的に聞かれたことを思ってもそれは確かである。罰を当てるのは勿論神仏であるから、何故、罰が当たるのか理屈は抜きである。説明は不要のアプリオリな行動規範が示されていたわけである。
どの宗教の聖典にも、いけない、ならない、という規範が書かれているが、何故であるかという説明は無い。人は神のみ心というものを信じて行動すると、よかれあしかれ行動に一貫性、あるいは言い訳ができて自分も他の人も納得できた。つまり、世の中に動きに統一性、自然な動きができたのである。
ダニエル・デフォーの「ペスト:Daniel Defoe, Journal of Plague Year,1722」を読むと、ペストがロンドンに蔓延して人々は狼狽の極に達しても、狼狽の中にも神のご加護を信じる気持ちが人々の中からなくならないでいたことが判る。悲惨な目に会っても、少しそれがやわらぐと神に感謝する気持ちが人々に強くなる。事実、ペストはロンドン市民の30%ほどを死亡させても皆殺しにはぜずに過ぎてしまっている。自然に免疫ができたのかどうか、不思議な事と言えば言えるわけである。
現代社会では神様任せという、この人類始まって以来の確固たる倫理の基盤は大きく揺らいでいる。人は神をおそれないようになったのである。我々は神罰を恐れなくなった。それに代わって、では何が拠りどころになったのであろうかといえば、勿論それはいわゆる科学技術である。果たして、科学技術は神に代わるご加護を人に与えることが可能であろうか?と考えると、誰しも恐ろしい気がするはずである。我々はたとえば遺伝子を組み替えて、食物を含む多くの‘新しい’生物を作ろうとしているが、そのような新しい生物がどのような性質を持ち得るのかは、判らない、のである。果たして、ペストがロンドン市民の半分を殺さずに過ぎたような‘自然の節度’を持たない‘新しい生物’が出来てしまわないかどうか、さわらぬ神に祟りなし、ではないか?
科学技術の成果が19世紀から20世紀にかけてあまりにも目覚ましかったので人々は、薬があれば病気が治る、ケイタイで魔法のように世界中の友だちと話せる、ちょっとお金を溜めれば自動車が買える、などの‘成果’に惑わされて、科学すなわち理屈、理性、の神に対する‘勝利’を暗黙の内に受け入れつつある。
神に対する不審、あるいは不信は先述のシジウィック等が始めた近代的な倫理学の基礎であるが、そのシジウィックも主著の結論として、なんらかの信念がなければ倫理はカオス(混沌)に堕ちるのだと言っているのである。最近では、新たに神様抜きの倫理を考えようとしたパーフィット(Derek Parfit: Reasons and Persons, 1984)は人が何を求めて行動するかをいろいろ解析して、神様抜きの新しい倫理の規範(理論Xと呼ぶ)を打ち立てようとしたが、当然ながら、結論には達する事ができていない。
結局、神は死んだ、と見ようとしてみても、神は死んでも死ななかった、という結論が出ようとしていると見ればよいだろう。
かといって、今の世の中を再び、敬虔な信仰によって動く世界に戻そうとしても、あるいはそこに倫理の理想を見ようとしても、そうならない事も容易に推量できる。神を殺すことは倫理上解決不可能な問題を生じる、事を理解したうえで、定言的命法によらない倫理について考えられて来たこと、考え得ることを次に検討する。
2.目的に合致した行動。
アリストテレスは、ニコマコス倫理学、と呼ばれる西洋における倫理学の最初の本を書いている。そこには冒頭に(1094a)、すべての技術(:テクネー)も研究(:メトドス)も善(:アガトン)を求めるものであるはずだ、と断言している。つまり善が行動の目的(:テロス)であるとしている。従って目的に何を設定するか、ということが倫理上の最も大事な課題となるわけである。
アリストテレスは目的について考えると、ある目的を達成するための当面の課題も目的である点に注意を払っている。例えば、お金は当面は衆人の目的だが、お金はそれで何をするかという手段だから、本来の目的とはならないものであると言う。
結局‘すべてを蔽うがごとき目的’すなわち究極の目的について考察することが、倫理上大切だと見るわけである。なぜなら、そのような究極目的なくしては、目的の系列は(目的の目的の・・・といったような)無限(:アペイロン)に続くことになり、なんの指針にもならないからである。
そして、そのような、究極の目的の対象となる善、最高善こそ‘幸福(:エウダイモニア)’であると言うのである。幸福が究極目的にふさわしい理由としてアリストテレスは、幸福はその事自身のために望まれるものであって、幸福になってそれを手段として別の状態を達成するような事柄ではないからであるとしている。
アリストテレスは勿論ギリシャ時代の人であるから、神話の神々を敬う気持ちがあった事は、どの著書を見ても判る。例えば‘形而上学’を少し読むと、哲学こそ何の役にも立たない学問であるが、それこそ最も‘貴い’ものである、その理由はこれこそ神の領域に近づこうとする(万物の原因について考えるというような)学問であって何かに拠りどころを決めてその上に便利で役に立つ学問を築くものではないからである、と述べている。つまり最上のものは‘神的’である、としているのである。
しかしながら、アリストテレスは倫理についての考察において幸福、という我々の生活上の感情、感覚を最高善と見ようとしていて、神の決めたもうた目的(例えば来世での至福)などには決して触れていない。しかし、人間が目的を設定するに当たって、目的の系列の無限性、とか、究極目的の定義(それ自身のための目的)などを考慮するところが、神の領域に近い、あるいは擬似的であれ神の業を模した事柄が倫理を考える場合に必然的であることを、はっきり認識しているのである。
そしてアリストテレスは幸福とは何かの考察に移って、それは、享楽的、政治的、観照的の三段階があって、その内の観照的(、contemplation, テオーレーテイケー)な活動が最高の幸福をもたらすものであるとしている。観照的とはわかり難い言葉であるが、その説明はされていて「人を導くような、うるわしく、神的なものについての想念・・・(1177a10)」がそれを意味しているようである。
このように、アリストテレスによって、人がそうあるべき望ましいあり方、すなわち倫理の基本が、神的という言葉は用いながらも、究極的とか、無限とか、の概念を神様にゲタをあずけずに、つまり宗教的にならずに提示されているにも拘わらず、西洋では18世紀中ごろから、はるかに程度の低い論議が倫理学の主流を占めるようになった。すなわち、功利主義的な発想が倫理と結びついたわけである。
功利主義(utilitarianism)はいろいろな形で多くの人が解釈しているが、端的にその発端としてベンサム(Jeremy Bentham, 1748-1832)をその代表と見てよかろう。彼のキーワードは‘最大多数の最大幸福’である(この言葉はイタリア人ベッカリアの、犯罪と刑罰、1764、による)。
功利主義による‘幸福’の概念は、アリストテレスのような深い考察もなしに、単純に人の享受する快楽(快、プレジャー)を意味している。端的にはより物質的に豊かであることが(お金の量で測れる)幸福である。アリストテレスから離れて一挙にこのようなよく考えるとムチャな発想を西欧世界がやすやすと受け入れた理由は簡単で、丁度その頃1700年代の中ごろから、いわゆる産業革命が始まったためである。
産業革命とは、それまで人間社会の利用していたエネルギー源は僅かな水力、風力を除けばすべて太陽の恵みで生育した食料によって支えられる人力、家畜力のみであった所に、蒸気機関による石炭エネルギーの機械力への変換が発明されて、一挙に桁違いの仕事が工業に利用できるようになった事態のことである(ニューコメンの蒸気機関は1712年、ワットは1769年)。
要するに、化石燃料利用による安易な生活を享受できるようになると、人はそのような本来人間社会のあるべきすがたでない自然環境の掴み取りを、あたかも人間が知恵により作り出した特権であるかのごとき観念を持つに到ってしまったのである。そうなると、お天道様だけに頼って生きていた時代は野蛮な生活であったと昔の生活を軽蔑して、少しでも多くの人が掴み取りの恩恵に浴することこそ幸福である、と信念をもって主張し、それが時代に迎えいれられたわけである。これが産業革命の実体である。
そのような幸福は自然環境の掴み取りの上に成り立っているのだと人類が気づくまでには300年近くかかったのだから、人間の知恵とは、そのようなものだと教訓にはなるであろうか。アリストテレス流に考えても、そのような幸福が究極目的でありえないし、実際問題として人類の居住性に適した地球環境は、はなはだ脆弱なのだから、エネルギーの掴み取りが長続きしないことも明白である。つまり功利主義的な幸福を目的とすることは、決して倫理的ではありえないわけである。端的に言って功利主義・倫理学という言葉はオクシモロン(撞着語法:悲しい喜び、と言うような反義語を並べた表現)と見ることのできるものなのである。
にもかかわらず、現代社会は殆ど従来と変わらず功利主義全盛の状態である。消費の活性化が世のため人のためである(最大多数の最大利益に合致)と臆面もなく発言する経済学者がいるし、それを利用する政治家もいるのである。最大多数の数え方は今生きている人の数だけでなく、これから生まれる人の数も数えるべきなのだが、そうすれば功利主義の発想においても‘最大多数の最大幸福’のためには我々は絶対にエネルギー大量消費による安楽の‘幸福’を享受できないのである。2000年以上昔のアリストテレスの論理にさえ対抗できない功利主義倫理学がそれでも幅をきかせ、研究されているのが現状である。
このように、目的を設定して目的に合致した行動が倫理に適っている、という見方も、最初にあげた神様に全てを任せる倫理によると同様の、社会がそうあるべき指針になり得るのである。しかし、アダム・スミスの経済理論に象徴される、人間の欲望を野放しにすることと、倫理との合致を探求、あるいは願望するようなことでは、倫理が破綻する(シジウィック、パーフィットの例のように)のは当然の帰結であることに気づかねばならない。(スミスは、商業の自由放任が、見えざる手に導かれて、世のため人のためになると主張する。国富論、The wealth of nations, 1776)。
最後にもう一つの選択肢(オプション)である、常識に頼る倫理について考えよう。
3.常識に頼る倫理
孔子はアリストテレと同じ古い時代の人だが、「論語」にその思想が凝縮されていると見て良いのだろう。論語を読むと、孔子は神様は敬うけれどもそれに頼ろうとはしていない(敬鬼神而遠之、鬼神を敬してこれを遠ざく、雍也)。いわんや自分自身はただの人であって、弟子を連れて旅していて食料がなくなって困ったりしたらしいことは、アリストテレスが庇護者のアレクサンダー大王が死んだらすぐにアテナイの学校をたたんで生まれ故郷のマケドニアに逃げたことと同様、ほほえましく親近感を覚える。
論語には、目的を設定してそれに向かう行動をとることが目的に適っている、などという自己矛盾を含むような論議は一切ない。人の行動については、そうするのが良い、というような説教があちこちに書いてあり、それぞれが、なるほど、と感心させられるものである。論語の中心思想を示すキーワードは‘仁’であると見て良いのだろう。では仁とは何か?と問わねばならないが、論語には仁者、すなわちこの‘仁’を達成した人の行いの具体例が盛りだくさんに示してある。これはなかなか上手い方法で、つべこべ理屈で説得するよりも‘事例集’が素人にはわかりやすい、まるでアメリカの技術者倫理のテキストのようである。
例えば「仁者先難而後獲、苦労を先にして利益は後、雍也」、「仁者不憂、仁者は憂えず、郷党」、「仁者其言也訒、仁者は言葉がひかえ目(訒:じん)である、顔淵」など、など、である。しかし事例だけはなく、説明もある。仁とは何かという弟子の質問に同じ答えが二箇所に見える。それの答えが、仁とは「己所不欲、勿施於人、おのれの欲せざるところを人に施すなかれ、顔淵、衛霊公」である。
特に後者にみえる弟子、子貢の質問は「有一言而可以終身行之者乎、一生実行していくべき一言があるでしょうか?」であるが、答えは「其恕乎(それは恕:ゆるすこと)である、己所不欲、勿施於人」となっている。つまり、仁とは、ゆるす、ことである、らしい。そして、ゆるす、ことが出来れば、自分のいやな事を他人に押し付けないですむのだろう。
この見方はニコマコス倫理学にあるメガロプシュキア(:メガロはおおきいこと、プシュキアは精神のこと、岩波文庫、高田三郎訳には‘矜持:きょうじ’となっている)という倫理的概念に似ている。矜持という言葉は電気学会の倫理行動規範の前文にも書かれているが、それは自分を最高の者であるとの意識でふるまうことであり、そういう意識を持てば孔子の言う恕、ゆるす、という行動も自然に出てくるのかも知れない。
さて、論語でそれほどまでに強調されている、己所不欲、勿施於人、であるが、この概念は世界中の宗教の聖典に必ずなんらかの形で書かれている。しかし、いろいろ詳しくそれらの原典を調べて見ると、はっきりと記録された記述としては論語が世界最古のようである。論語は後世に儒教という思想の中心テキストとなったので、ある意味では宗教の聖典の一つとも言えなくもないが、論語そのものを読めば先述のように、神様の権威を借りて、己所不欲、勿施於人、という規律あるいは戒律を実行しなければ罰が当たるぞ、という雰囲気は全く無い。
論語はいずれの章句も、弟子達の素朴な質問に、私はこう思うよ、というような私見の披瀝のように読める。つまり、第一のセクションで見た、定言的命法:カテゴリカル・インペラティブというような、天から降って湧いた教訓ではない。端的にいえば、当時最高の常識人の知恵すなわち、社会の動きと人の本性との観察から得た最大公約数的振る舞いの基準が示されているのであって、無限を引き受けて下さる神様にもよらず、目的がこうだから矛盾なく究極目的と出来るのは幸福である、などと屁理屈は必要としていない。これしかない行動の規範の根幹が押さえられて、人間の本性の透徹した理解とそのマネージメント術の極致がこの常識の中の常識に凝縮されたのであろう。
孔子によって最初に書かれた「おのれの欲せざるところを人に施すなかれ」という言葉は新約聖書、マタイ伝、ルカ伝、には‘人からして欲しいことを、あなたも人にしてあげなさい’と違った表現で現れていて、西洋では倫理の黄金律、ゴールデン・ルールと言われている(表現の違いのもつ意味などに関しては‘黄金律と技術の倫理’開発技術学会叢書、2001、新宮秀夫、参照)。しかし、どの表現の仕方の場合にも必ず、自分と他人、とが含まれている。すなわち黄金律は自分がこう「ある」べきだという倫理的行動規範を超えて、他人との関係に踏みこんでいる所に特徴をもつのである。つまり、自分だけが、よし、という身の処し方の注意では事足りず、他人に対して自分が「する」ことも正しくあるべき必然性を感じた時に出てきたのが黄金律なのである。
孔子がこれに目をつけたのは恐らく当時の社会が、その中での人間関係がどんどん発達してきて、各個人が自分の身を律するに当たって、人との間柄に特に注意が必要になり始めた時期に当たっていたためであろう。和辻哲郎は倫理学とは‘間柄’の学であるとしているが(人間の学としての倫理学、岩波全書、1934)まさに黄金律は間柄の重要性に人が気づき、それを律する基本を述べたのであろう。
黄金律は論語の例を見ても、神を前提の倫理や目的設定の倫理のどちらにも現れる無限の質問の系列や、絶対的な拠りどころを明確に示しているわけではなく、いわば常識的言葉である。しかし、そのような極限的なものなしに、この言葉が世界中で知られて、規範として理解され得る理由は、それが、自分と他人とを置き換えて見る、という知恵に根ざしているためである。英語でこれは、reciprocity、と称されるが、自分と他人との立場を変換すると、その人と更に別の人との関係も同じルールで事がすみ、関係が無限に尾を引くこともない。という利点があるのであろう。アダム・スミスが繰り返し書いている‘公平無私な第三者(impartial spectator)’に道徳的判断を求めるという発想も、相手の立場に立って見るという知恵によれば、よりたやすく実行できるのである(The theory of Moral Sentiments, 1759)。
以上見てきたように、神頼み、目的設定、常識的、いずれの方法によっても、人と社会の運行を好ましく調整する事の出来る倫理の構築が可能であり、その場合に必然的に要求される、規範の絶対的根拠と理由についての無限に続く問の系列、への対処法があり得ることが分かった。
詳しくみれば、三つの方法は異なるようではあっても、例えば神頼みの定言的命法にしても、実は神様が規範を教えてくださる訳ではないから、始めは常識的な命法を人間が常識で考えて、それを神様の言葉に祭りあげる所から始まったのである。しかし、一端祭りあげれば、それは人間が作ったか否かはもう問題でなくなり、それはアプリオリ、な定言的命法となるわけである。つまり、上記の三つの区分は人間の見方として、区分される意味がある、というわけである。
最後に、これらを纏めて、神頼みであれ、目的としてであれ、常識であれ、倫理の目的として人間が何を求める生き物であるのか、今、なにが最も重要な倫理的な規範であるのかを考えよう。
4.総括
宗教の目的は信者が至福を得ることである。次に、目的設定によって倫理を説くなら、例えばアリストテレス流によれば、幸福達成に向かって行動せねばならない。さいごに、常識的に行動するならば、仁を達成して憂いのない生活を目指すべきことになる。
いずれにせよ、結局、具体的にどんな状態を目指すことになるのか?そこが示されなければ、本稿もただの解説に終ってしまう。アメリカの技術者倫理のテキストが、あまり高尚なものではなくても、世に広まった理由は、原理的な考察抜きの纏め方でも誰にも分かる事例を満載した為であろう。読めば、なんだそんな事オレならしない、と思う人が多くても、そう思ってくれる人がいれば本は大成功である。実際、それらの本が沢山の人に読まれたのだから、それによって自分の行動に自信を持った技術者も多く出たに違いない。
ここでは、もう少し高尚な立場、すなわち、やや抽象的な立場に立ちながらも、人の求めるもの、それを幸福と呼んで、それが果たして功利主義者による豊かさ、快楽であるのか、アリストテレスの言う観照的生活なのか、論語にある憂いの無い生活なのか、はたまた、神頼みが一番で全てを神様任せが良いのかを具体的に考えて見よう。
アリストテレスは人間の求める幸福が、最も高尚な観照的生活であって欲しいという願望からこれを最高の幸福とした。よく考えると確かに享楽的な快や政治的(名誉)の仕合せより、深く物事を観察して考える幸福の方が人にとってより喜ばしいかもしれない。しかし、誰でもがそのような高尚な幸福を味わいたいか、また味わえるかと考えると、やはり願望は願望でしかない、とも見える。
一方、功利主義者の幸福は先述したとおり、快楽を臆面もなく幸福として、しかもその量が多いほどつまり快楽に浸れば浸るほど幸福度が上がるとしている。これは世に溢れている出版物や、新聞記事、テレビの番組などを見れば正に現代社会の幸福解釈そのものである。
ほんとにその見方が正しいのなら、もう人類に先があまり無いことは確実である。つまり本当に我々は安易な生活を出来れば幸福なのであれば、今のままの、エネルギー浪費、自然環境掴み取り、具体的には消費の活性化と経済発展を続けて破滅するより仕方が無いのである。
しかし、よく世間を観察すると、実は人間の幸福は、功利主義者の思っているようなものとは全然ちがうのである。エネルギーを掴み取りしている国は平均寿命が長い、というデータを見て、エネルギー浪費こそ幸福をもたらす、と見る人もいる。しかし、その寿命の中味はどうであろうか?果たして我々は50年前に較べてエネルギーを10倍ほども使うようになって平均寿命も十数年延びた分だけ幸福になっているだろうか?そのような‘幸福’な国でなぜ自殺者が年に三万人、交通事故死者が一万人もでるのであろうか?
生きることの楽しみ=消費の享受+余暇の享受-仕事の苦痛
という方程式を書いた学者がいるが(The Entropy Law and Economic Process, エントロピー法則と経済過程、Nicholas Georgescu-Roegen, 1971)功利主義に基づく西洋の今の社会思想はこれを受け入れているのである。しかし、アリストテレスは、アナカルシスという先輩哲学者の言葉を引用して、人は仕事の中にこそ幸福をみいだすのがよい、余暇は仕事を楽しくするためにあるのだ。と書いている(1176b30)。どちらが正しいのだろうか、答えは想像や推量でなくて、17世紀頃からいろいろ研究され実験までされた人間の本性のなかに見出される。
これについては別に論じたので詳述しないが、要は人間は何事につけ、不足において元気が出て喜びも大きいという本性があり、満ち足りてしまうと途端に意欲が減退して喜びに鈍感になり精神的にも肉体的にも不幸になるのである。
その原理は、賭けの利得の感じ方に関するベルヌーイの考察(セントペテルスブルグ問題)やウェーバー・フェヒナーによる人の感覚の閾値(いきち)の実験、さらに新古典派経済学における限界効用理論(marginal utility:一言でわかる経済学、電気評論、2003年9-11号、新宮秀夫)など、人間の本性に基礎を置いているのであるが、ここでは、それらを論じた結果を、感動の幸福と、豊かさの幸福について概念図で示す(エネルギー節約は最大の資源・幸福の基礎、エネルギー・資源、Vol.27,No.2(2006) 。 電気評論、2006、臨時増刊号、新宮秀夫)。
ここに示すとおり、確かに物が豊かになれば生活は楽になり幸福は増すが、それにつれて感動の幸福は感じ難くなるのである。少しでも昔の生活を知る人には容易に下記の図が理解できるはずである。もっと突っ込んで言うならば、悲しみは笑いに勝る(旧約聖書、コヘレト, 7-3)という見方さえ出来、そのことを人類は古くから知っているのである(幸福ということ、NHKブックス、838、1998、新宮秀夫)。
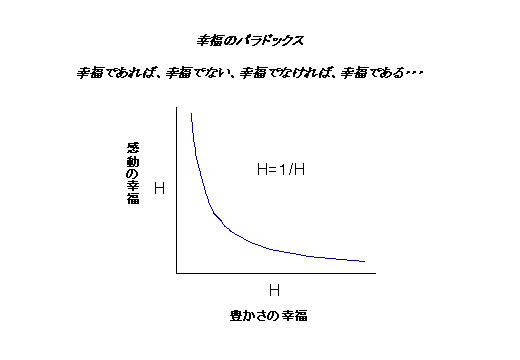
このような幸福の見方に立てば、功利主義倫理に基づく理性的な倫理学の構築の試みが無駄な努力であることが分かるであろう。ここに示した幸福の見方には、冒頭に挙げた、倫理の三つのアプローチの仕方に共通の、何故それが正しいのか、という倫理学に必然的に付随する問に対する答え、すなわち無限の問の系列をしのぐこと、そして、‘絶対’をどこに求めるかについての考察が含まれている。つまり幸福が、不足においても充足においても、たやすく無限に近付き得ることが容易に図から読み取れるのである。この見方を基礎にして、従来の倫理学の流れを見るならば、今倫理に求められている事が何であって、どう対処したら良いのか見通せるであろう。
以上で、倫理は人間の本性に基づいて構築すべきであって、そのやり方は、絶対的な基準と、それを設定する理由に対する無限系列的な問い、に対処さえできれば、定言的命法(神に任せる方法)によるもよし、目的を人間の幸福におくもよし、相互性(reciprocity)に基づく、仁、こそ基本で矜持を保った生活を心がけるもよい、ことが分かった。それらはいずれによっても、人間の本性に基づく幸福と一致した社会活動の指針、すなわち倫理の規範を示せるのである。
最後にしかしながら、今最も大切な考え方、具体的な行動を求められている事柄を強調して終わりにしたい。
ローマの諺に‘Primum vivere deinde philosophari、先ず生きること、哲学はそれから’というのがある。命あってのものだね。とでも訳せるのだろうか?倫理も哲学の内と見れば、行動の規範について細かく理解し勉強するのも、時間があれば良いけれども、今は差し迫った危機対処に全力投球が要請される時代なのだ、ということに気づくことが大切なのである。
端的にそれは環境危機の現実である。みんな普通の生活をしているからまだ危機は先と思っているのが我々皆の態度であるが、夕張市の破綻は危ないとは思っていても今すぐとは誰も予想していなかった。あれは夕張だけ、と思っているのは自由だが、日本全体を見れば、夕張以上の借金づけである。国家予算の10倍とか20倍とか借金を抱えてまだ消費の活性化を唱える政治家がいる。経済発展をしないと借金が返せないという理屈であるが、その借金は経済成長の結果出たものだったのではないか?環境破壊による人類生存の危機も同様である、他の事柄と違って、これは‘気がついた時には手遅れ’であってはならない。
要するに、環境も経済発展も、というウインーウインの社会など決して無いのである。環境を守るならエネルギー消費の大幅削減以外に方法はない。そして、環境が破壊されれば人類に未来はないのである。産業革命以来の悪習であるエネルギー大量消費社会を正さねばならいない。エネルギー節約の社会は環境負荷を減らすと同時に人の幸福にも資することは先述した。要は、あらゆる手段での節約の実行こそ今最も求められている倫理であって、これは人類の生存の問題である。生存が続いてこそ、その上の高尚な倫理をも論じる事ができるのである。取りも直さずPrimum vivere deinde philosophariなのであり、今とり上げるべき、一言でわかる倫理学はこれなのである。
Written by Shingu : 2007年10月02日 16:00